超左翼マガジン『ロスジェネ』編集長として知られる作家の浅尾大輔の4年ぶりの新著は、なんとマルクスである。〈『新解 マルクスの言葉』(バジリコ・1700円+税)〉長い雌伏期間も、マルクス・エンゲルス全集を読破し、当時の思想家や現代の作家や経営者の著作など、関連文献も広く渉猟するためであったとすれば、うなずける。
マルクスの数多くの著作・手紙・覚書の中から、作家の感性で、きらりと光る宝貝のような言葉を268選び出し、その一つ一つが現代にどのように生きているかについて解説的エッセーを書いた。リーマンショックに揺れブラック企業が跋扈する現代の世相から、『もしドラ』のドラッカー、フリードマン、勝間和代まで、幅広い話題を自在にひいており、教条的なマルクス解説には飽きた読者も、その新鮮さに目を見張るだろう。 かびくさい書庫の片隅からマルクスの言葉を救い出し、広い世間に解き放って武者修行を試みたところにこの本の最大の功績がある。
マルクスをその思想的発展の中で読まず、初期から晩年までの著作を並列的に論じていることを弱点と考える人もいるだろう。しかし、マルクスほどの古典になれば、アプローチの仕方はさまざまにあっていい。様々な読みの試みとして重要だと思う。
「あとがき」によれば、本書の企画は2年ほど前に出版社の依頼から始まった。マルクスの言葉をバラバラに抜き出したうえで解説をつけるというベストセラーの『ニーチェの言葉』に近いものだった。浅尾は2008年6月8日の秋葉原事件と、2011年3月11日の東日本大震災とにかかわる二つのルポを書いている傍らで本書に取り組んだそうだ。後から始めたマルクス本の方が先に完成したわけだが、二つのルポもぜひ早く完成させてほしい。おそらくマルクスに取り組んだことが生かされるのではないかと期待する。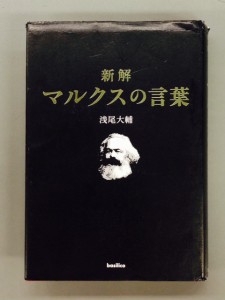
これからその内容に分け入っていくが、少々長くなることをお許し願いたい。なにせマルクスの哲学・経済学・革命論のエッセンスを凝縮した本なのだから、ひとたび個々の内容に立ち入るなら、通り一遍に済ますわけにはいかない。時間のない方は、ここまでで終わるか、太字にしたマルクスの言葉の興味を引いた個所だけを拾い読みしていただきたい。
なお読んでいくと、マルクス・エンゲルス全集の生硬な翻訳が、敷居を高くしていると強く感じる。くしくも本書出版の翌月には、漫画評論家の紙屋高雪による『超訳マルクス』(かもがわ出版)も出版された。こちらは解説をつけるのではなく、訳文そのものをかみ砕いてマルクスを若者に身近にしようとしている。ロスジェネ世代の旗手がほぼ同時にマルクスの現代化に取り組んだのは偶然以上のものを感じる。両書を合わせ読むのも得るところが多いと思う。
さて詳しい内容に入りたい。全5章の中の第1章「すべてを疑え」は、哲学篇である。
◆すべてを疑え。(p.8 以下、太字はマルクスの言葉)
浅尾は「マルクスは、娘のジェニーから『好きな言葉は?』と問われて『すべてを疑え』と答えた。彼の人生観を表現したものだ。(中略)二〇一一年三月一二日、福島第一原発が爆発した後の私たちは、政治家と学者の言動に『騙された!』と思った。(中略) 疑うとは、自分の頭で考えること。そして我が身を振り返ること」とコメントしている。
卑近な蛇足ながら、これはすべての推理小説のスローガンでもある。浅尾大輔の本書と並行して。たまたまアガサ・クリスティーのミス・マープル・シリーズの一つ『書斎の死体』を読んだが、誰も疑わなかった話の前提となる証言がウソと分かってショックを受けた。やはり「すべてを疑え」である。閑話休題。
◆ラディカルであるとは、ものごとを根本から掴むことである。(p.10)
浅尾「『ラディカル』という言葉には『過激』という意味がある。しかし派手なパフォーマンスとは無縁なマルクスは『根本的』という意味で使っている」。同時に、浅尾は「マルクスにとってラディカルであるとは、社会を変える新しい人間像を提示することだった」と書く。「ラディカル」のなかに「新しい人」を読み込む視点が新鮮だ。それは、敗戦後の『播州平野』で明日を築く活力を持った人を美しく描いた宮本百合子とも通じる。震災後の日本に求められていることだ。
◆宗教は、悩める者のため息であり、心なき世界の心情であるとともに精神なき状態の精神である。それは民衆の阿片である。(p.11)
「宗教否定」とされる、若きマルクスのこの有名な言葉について、浅尾は「この言葉には、批判者マルクスが新しいビジョンを構築できないジレンマも滲んでいる」と読む。そして今「『宗教』という絶対的価値にとって代わったのは『お金』『土地』『株価』という名の『阿片』ではないのか」という。 マルクス主義の非情と硬直性の代表のように扱われてきた言葉の、見事な読み換えではある。「お金」や「株価」が現代の民衆のアヘンだということは、アベノミクスで株価が上がったおかげで、自民党の支持率が上がったところに遺憾なく示されている。
◆匿名ということは、話し手だけでなく、公衆をもより公平にする。(p.33)
浅尾は、「自己責任論批判」(p.13)や、売れっ子女性経済評論家の「落ち込んだときは、ゆっくり寝て、太陽の光をたくさん浴びて笑えばいい」という現状肯定の気休めを退けて「改革派と称する知識人は、概して保守主義者だ」と喝破する(p.21)。
「生活が意識を規定する」(p.22)という唯物論的人間観や、階級とは何かという史的唯物論の基礎も明らかにする(p.26)。 そうしたマルクス主義哲学の基礎をわかりやすく論じながら、「匿名」についてのこの言葉に寄り道して、現代のツイッターなどのSNSの隆盛がここに予言されていると指摘する。「ツイッターで拡大した脱原発デモは、かつてマルクス記者が農民の貧困を伝えた記事で政府を揺るがした大事件と同じ現象なのかもしれない」と。(SNSについては第5章のところで詳述する)
◆豊かな人間とは、人間的な生活表現の全体性を必要とする人間のことである。(p.75)
浅尾は「マルクスは『仲間内のお遊びは終了!』と宣言したのだ」(p.36)とか「マルクスは罵詈雑言の人である」(p.39)などと、数々のシャープなコメントをしている。東日本大震災と福島第一原発のメルトスルーが国民の意識を変えたこと(p.37)や、入社二カ月で過労自殺した「和民」女性社員の日記をひいて(p.44)、マルクスの「実践」の思想を現代に引きつけて考える。 また、マルクスの学位論文はギリシア哲学に関するもので、「デモクリトスの自然哲学とエピクロスの自然哲学の差異」だった。浅尾はこの学位論文を読むと「目前にそびえるプロイセン王国がいかに砂上の楼閣かという自身の直感を必死で立証しようとする様子が目に浮かぶ」(p.56)という。「若きマルクスの課題は、宗教の力を借りずに社会を変えるというプロジェクトだった」(p.69)とも書いている。
そして、社会を変える担い手を求め続けて、マルクスがたどり着いた結論を、浅尾は上記の言葉に託して解説している。「若きマルクスが構想した『共産主義』は、資本主義的な人間性を知悉(ちしつ)し、それを乗り越えようとする『豊かな人間』が担うものだった」。それはどういう人間か、浅尾によれば第一に「資本主義の豊かな商品世界と貧しい暮らしを経験した人びと」、第二に「エゴイズムを身をもって知りつくした人間」、第三に「新しい考え方と生き方の模索は……自発的な感情が人間を突き動かすのでなくてはならない」という。エゴイズムこそ、それを出発点にして他人の必要性に気付き、「連帯を求める社会運動につながるモーメントだ」という。かつての全共闘のスローガン「連帯を求めて孤立を恐れず」を逆転させたような論理展開だ。
「マルクスは、資本主義を否定したのではない。そのなかに次代を担う新しい人間の萌芽を見つけようとしたのだ」と浅尾は書いている。ここにマルクスの哲学研究の結論と、経済学研究の出発点が端的に語られていると思う。
◆フォイエルバッハはヘーゲル弁証法に対して批判的な態度をとり、総じて古い哲学の真の克服者である。(p.76)
本書全体を通して、浅尾はマルクスを一人だけ孤立させて読んでいない。マルクスが読んだ先行思想家や、影響を与えあった同時代の思想家、そして後世から現代の思想家・著述家、経営者。そうした人々の間に置いて、相互に関連付けながら読んでいる。そこに風通しの良さと視野の広がりを感じる。
特に哲学の本章ではマルクスに影響を与えた思想家を丹念に読んだエッセンスを生かしている。直接に大きな影響を受けたヘーゲルはもちろん、プラトン、アリストテレスという哲学の源流である思想家(p.31,p.58,p.72)、「現実的実証的な学」として模範にしたルソー、アダム・スミス(p.23)、カント、ベンサムなど、きら星のようだ。
なかでも高く評価しているのはフォイエルバッハ。もちろんエンゲルスの『フォイエルバッハ論』で、マルクス主義を学ぶ者にはおなじみの名前だが、浅尾はフォイエルバッハを直接読んで、その思想を高く評価している。また妻イエニーがマルクスの部屋を掃除中に「あなた、しっかり保管して頂戴」と叫んだバラバラの紙片こそ、フォイエルバッハからの引用メモだったエピソードを紹介している。
大学を追われたフォイエルバッハは貧困のうちに死んだ。「晩年の著書では、貧困が人間性を奪うと記し、〈『資本論』を参照せよ〉と書き記していた(城塚登『フォイエルバッハ』勁草書房)」そうだ。フォイエルバッハが『資本論』を読んでいたとはびっくりした。ちなみにフォイエルバッハは『資本論』出版の5年後に68歳で亡くなった。
◆私は語った、そして私の魂を救った。(p.80)
何も堅苦しい言葉ばかりではない。浅尾はマルクスのエンゲルスへの金の無心の手紙を引用したり、マルクスの病気の話をひいたり、偉大な思想家の人間臭い一面もとらえている。そして、「著作家は、必要とあれば、著作の生命のために著作家自身の生命を犠牲にするほどである」(p.47)というマルクスの言葉を引いたページでは、特高の拷問をうけて屈服よりも死を選んだ小林多喜二について書いている。
「私の魂を救った」というのは、自己満足のために書いたというわけではない。自分のなすべきことを果たしたという充実感を語っているのである。浅尾は「いま、私たちが心に刻むべきは、自分を裏切らないマルクスの誠実さとラディカルさである」とまとめている。
第2章「商品の命がけの飛躍―価値の本質」、第3章「プロレタリア諸君、団結せよ―資本家対労働者」、第4章「大洪水よ、我が亡きあとに来たれ!―資本主義の正体」は経済学篇である。
◆資本主義的生産様式が支配している諸社会の富は、「商品の巨大な集まり」として現われ、個々の商品はその富の要素形態として現われる。(p.84)
経済学篇は『資本論』の書き出しのフレーズから始まり、マルクスの価値論をたどっていく。価値論はマルクス主義経済学の入口にして最大の難関である。著者の浅尾もかなり苦労したようだ。
「商品と価値とは何か。『使用価値』と『価値』である」(p.84)「マルクスは商品の価値を『使用価値』と『交換価値』に分ける」(p.88)「商品の価値とは、何か。マルクスは『人間的労働一般の支出』という」(p.90)。「何事も最初は難しい」とマルクスも言ったように、本書のカチカチ山もなかなか険しい。こうして並べると矛盾しているようだが、それは1頁読み切り形式で仕方がないところで、読者はあまり細かいところにこだわらない方がいいだろう。
例えば「商品の価格は、需給バランスが決める」(p.95)と書いた次のページに「『商品の価値』は実は、需給バランスで上下する価格ではない」(p.96)とあって、混乱するかもしれない。これは「価格」と「価値」の違いに気づけば、一応は解決する。いずれにしても『資本論』第3巻の「生産価格論」からすればまだ初歩的な理解ではある。いずれにせよ、通して読めば、浅尾が「商品の価値」の実体に一歩一歩迫っていることは見て取れる。
◆商品の価値対象性は、どう掴まえたらいいかわからないことによって、寡婦(やもめ)のクイックリーと区別される。(p.99)
価値論で頭が痛くなった読者のために、ちゃんとコーヒーブレイクも用意してある。 これは価値のつかみにくさをマルクスがユーモラスに語った一節だ。浅尾は「寡婦のクイックリーとは、戯曲『ヘンリー四世』の登場人物だ。作者のシェークスピアは、とらえどころのない不信心な悪女の存在を『魚でも四足動物でもない。ゆえにカワウソみたいだ!』と書いた」と紹介している。
そのうえで浅尾も別の絶妙な比喩を出す。「私が商品の『価値』を想像する時、漫画『ドラゴンボール』の『元気玉』を思い浮かべる。目前の商品から素材や有用性、工程を剥ぎ取れば、労働者の精神的肉体的パワーだけが集中した一点『労働の凝固体』が残る。それこそ『元気玉』にふさわしい」
◆かくて「領主のない土地はない」という中世的ことわざに、「金に主はない」という当世流ことわざがとってかわる。(p.108)
第2章の最後で、浅尾はマルクスの未来社会論を紹介している。 「マルクスは、目を輝かせて未来を語っている。『いつの日か土地所有は廃止され、営利の対象でなくなる。労働者の協同組合方式のもと、もう一度、人間の情緒的な所有物へと生まれ変わる』君は、夢物語と思うかい?」
こうしてみてくると、マルクスのロジカルな価値論にロマンチックな服を着せたところに本章の取柄があるといえるだろうか。 ただし「弁護士の一時間の相談業務と自動車工場での一時間の検査業務とが同じ価値をもつという認識が透徹した社会。それが共産主義だ」(p.112)とあるのには異議を唱えたい。マルクスは単純労働と複雑労働、肉体労働と精神労働の違いによって、同じ労働時間でも異なる大きさの価値をつくることを認めていた。また、弁護士業務のようなサービス労働は価値を生まないとマルクスは言っており、今日も論争問題である。
また、「若きマルクスの『共産主義』には、お金が存在しないという。おそらく『求めよ、さらば与えられん。探せ、さらば見つかる。門を叩け、さらば開かれん』(『マタイ伝』)のイメージだろう。私たちには、まだ遠い世界のようだ」(p.109)とあるのも、注意が必要だ。今日の理解では、未来の共産主義社会でも市場経済は残る。ということは、お金も残るということである。
かつてソ連や中国で無理やりの貨幣の廃止が経済の混乱と後退を招いたようなことは、もうやらないのが現代の革命勢力の見通しである。
◆労働者が身をすり減らして働けば働くほど、彼自身に属するものはますます少なくなる。(p.118)
「万国のプロレタリア諸君、団結せよ!」(p.114)「労働者は祖国をもたない」(p.116)などの有名なマルクスの言葉に、浅尾は現代的な解説をつけているが、ここに掲げた言葉には、石川啄木の「はたらけど/はたらけど猶わが生活(くらし)楽にならざり…」の歌からはじめて、文学的解説をしていて面白い。『女工哀史』にもふれながら、最後は山本茂美『あゝ野麦峠』から、こう書いている「一九〇九年一一月、兄に背負われた女工政井みね(二〇)は、岡谷製糸から帰る野麦峠で、『ああ、飛騨が見える』と言って亡くなった。若い命の結晶である生糸が、商品になるや否や悪魔となって彼女の命そのものを奪ったのだ」
◆労働者は、人格化された労働時間以上の何ものでもない。(p.124)
『資本論』も「価値論」を終え、過酷な労働や資本家の搾取の具体的な話になると、浅尾の筆も俄然精彩を放ち始める。「派遣」「請負」は「人格化された労働契約」、「偽装店長」や「なんちゃって公務員」(臨時公務員)は「人格化された労働基準法違反」と皮肉もさえている。
そのほか、失業者についてはユニクロの柳井正会長の社員使い捨ての言葉をひく(p.122)。資本家が労働者に施す「奴隷になるための教育」については「マルクスなら問い返すだろう、『なぜ先進国日本では労働法が教えられていないのか』と」と記す(p.123)。「労働者の使用価値の前貸し」(マルクス)については、浅尾自身が応募したトヨタ自動車の期間工体験から、最初の給料日前に相当額の出費が必要となることを示す(p.131)。このように優れた解説が目白押しだ。
そして、労働者の自由とは、資本家に生殺与奪を握られた自由であり、会社の利益追求のために酷使される自由であることを示す。マルクスの「蚕は完全な賃労働者ということになろう」(『賃労働と資本』)を引いて、労働者は「繭」という生産物をつくるために、「桑の葉」という賃金を与えられている蚕と同じだと喝破する(p.126)。
◆資本とは、生きた労働を吸収することによってのみ吸血鬼のように活気づき、より多く吸収すればするほど活気づく、死んだ労働である。(p.140)
これは『資本論』のなかでももっとも有名な言葉の一つだ。機械油と石炭が匂う19世紀の工場労働だけでなく、清潔な現代のオフィスでも同じだと浅尾は書く。「始業前に見る職場の風景こそ『死んだ労働』である。死んだふりをした『資本』という吸血鬼は、君がパソコンを立ち上げた瞬間、君の首にかぶりつく。(中略)職場の人々全員に『死んだ労働』はゾンビとなって噛みつき、彼らの『生き血』がどんどん資本家の懐へと流れていく」
◆労働者は自分のためにではなく、資本のために生産する。(p.162)
この言葉につけた浅尾の解説は、マルクスが乗り移ったかのような怒りが満ちている。 「『給料とは、ギリギリの生活費である』(マルクス) そんな彼は叫ぶだろう。『ユニクロ社員4200人は柳井正会長の財産を築くために、ワタミ従業員6100人は渡邉美樹・元会長の私財を肥やすために懸命に働くのだ!』と。(中略) 自給自足の原始人や共同生活を営んだ古代人は滅び去った。 いま私たちは、世界一の儲けを目指す資本家のために生きているのだ」 これ以上の補足は不要だろう。
◆我が労働者は生産過程に入った時とは違うものになって、そこから出てくるということを認めなくてはならない。(p.170)
これは『資本論』のなかでも最もボリュームのある「労働日」の章のしめくくりの言葉だ。長いたたかいの末に、一日10時間という労働時間立法を勝ち取った労働者たちのことを語っている。浅尾もこの言葉を第3章の最後においている。労働者の団結の巨大な可能性と、困難を語って含蓄がある。「だからこそマルクスは、労働者が団結することほど難しいことはなく、それゆえに巨大な力を発揮するということを知っていた。団結するための簡単な方法などない。団結の法則などないのだ」
◆富を増加させながら貧困を撲滅できない社会、人口よりも犯罪が急速に増加しさえする社会体制の核心には、何か腐敗したものがある。(p.189)
さらに第4章では、新しい技術の適用が労働者をどう追いつめ、資本家を富ませるかについてIT技術など様々な今日の例をあげて、マルクスの分析が現代に通用することを豊かに明らかにしている。その視野は現代の社会問題全般に広がっていく。恐慌の原因と労働者の状態 (p.180-181)、資本主義と犯罪(p.189、掲出句)、原動力革命と原発(p.195)、ブラック企業がはびこる背景に、労働行政の切り捨てがあること(p.218)、経済発展と精神病増加についてマルクスの恐るべき予見(p.219)、「労働者の賃金上昇を相殺する」インフレのトリック(p.220)、機械と工場(p.223-227)、労働規制立法の必要性(p.229)、貿易と為替レート(p.230)、投機の横行(p.236)等々。その話題の広がりは目を見張る。
ただ一部で著者・浅尾の勘違いも見られる。労働の密度の強化は絶対的剰余価値の生産にあたること、また社会全体の生産力(とくに労働者の生活資材の生産部門の生産力)が上がって得られる「相対的剰余価値」と、個々の企業の発明・改良によって社会的平均的生産力の超過分によって得られる「特別剰余価値」は別物であることを指摘しておきたい。
枚数もかなり長くなってしまったので、急ぎ足で最後の第5章「このひき蛙どもを見ろ!―階級闘争のイデア」にすすもう。この章は革命論である。
◆人々は、ナポレオンが溺れる群衆を眼下に指さしてその従者に「このひき蛙どもを見ろ!」と呼びかけたと、陰口をきいている。(p.243)
「これまでのすべての社会の歴史は階級闘争の歴史である」(p.240)や“歴史は繰り返す”の元ネタ(p.242)など、人口に膾炙した文句から革命論を始めている。掲出句は見たことがなかったが、浅尾が“アニメ「天空の城ラピュタ」のなかの、悪役が「見ろ人がゴミのようだ!」と高笑いするシーンを思い出すだろう”と書いていて、思わず笑ってしまった。マルクスが宮崎駿と同じような場面を描いていたとは知らなかった。
浅尾は「この言葉には、権力者に黙って従う官僚と、彼らに支配される国民を待ちうける悲劇が込められている」と書き、「友人たちが『国民はバカだ』と嘆くのを」マルクスは次のように諭したという。 「彼等は、絶望なんかしていない。この国の希望は、弾圧されても考え、悩み続ける人間が残っていることなんだ」。安倍自民党の大勝と反原連の官邸前行動という相反する二つの現象が共存する、現代日本の隣人としてのマルクスを一番感じるセリフではないだろうか。
◆現在の社会は決して固定した結晶ではなく、変化の可能な、そして絶えず変化の過程にある有機体だという予感が、支配階級の間にさえ目覚め始めている。(p.245)
そう思ったら、浅尾も同じことを考えたようで、2ページ先で『資本論』初版序文のこの言葉を掲げて、官邸前行動に言及していた。浅尾は「変化の潮目に敏感な支配階級の『目覚め』の一例」として、官邸前に20万人が押し寄せた2012年6月30日のソフトバンクの孫正義社長の行動を書いている。孫は「がんばっている皆さんを少しでも応援したい」とツイートして、携帯回線のパンクを避けるため国会前に基地局を出張させたそうだ。 ここで私は、脱原発を公言している小泉純一郎元首相も、支配階級の「目覚め」の一例として思い起こした。
◆私が言おうとしているのは、現存するいっさいのものの容赦ない批判である。(p.250)
浅尾はマルクスの言葉に立ち返って、世間に流布している革命のイメージを次々と訂正していく。そのすべての言葉を挙げることはできないが、例えば青年マルクスは自分たちが「真理の独裁者」としてふるまうことを否定していたことにふれ(p.247)。ただ一つだけ条件として「この仕事は、協力によって成しうる事業なんだ」と書く(同)。
あるいは「翻って『革命』はあたかも禅寺の長い階段をみんなで登っていくイメージとなる。国民の自発性に基づく革命でありながら、実現された革命は、私たちの感覚にしっくりいくものでなければ反故になる。/青年マルクスは、理想主義者というよりリアリストだ」(p.248)と書く。 そして掲出句を挙げて、実現不可能な空想にふけりユートピアを夢見る、同時代の革命家たちにいらだっていたマルクスの姿を明らかにしている。そして現代のエセ革命家たちをも「革命は、未来からはやって来ないのだ!」としかりつけている。
◆我々が共産主義と呼ぶものは、現在の状態を廃止する現実的運動のことである。(p.255)
この言葉も前項に続いて、革命はユートピアを目指すものではなく、現実から出発するものだと語っている。全体を通して浅尾の強調点がどこにあるかは明らかだ。 浅尾は、マルクスが共産主義を目指し、労働者が資本家に最後は勝つことを確信しつつ、「マルクスが『資本主義』を否定していない点も注目に値する」(p.258)と注意喚起している。 私が冒頭に紹介したように、浅尾が「マルクスは、資本主義を否定したのではない。そのなかに次代を担う新しい人間の萌芽を見つけようとしたのだ」(p.75)と書いていたことを思い起こそう。
「思うに、マルクスの『共産主義者』『共産党』の任務は、共産主義国の建設ではない。資本主義を根づかせ、可能な限り平和的な平等を実現することだった」(p.265)とすら言っている。これだけでは誤解を招くが、要は見かけの体制チェンジの有無よりも、内実の要求実現が大事だということだろう。国民を抑圧する「社会主義国」よりも、民主主義と基本的人権を保障する資本主義国の方がましだ。浅尾も日本では『共産党宣言』の7割、「ドイツにおける共産党の要求」の5割が実現していると評価している。
そう考えれば、共産党の世界的退潮が押しとどめようもなく続いている中でも、マルクスの目指した労働者の解放は一歩一歩進んでいるとみることもできる。歴史は必ずしも、予言通りには進まない。「もはや社会主義ではなく、資本主義だ」といわれる中国も、それほどマルクス主義から遠く離れてはいないのかもしれない。
◆インターナショナルとは労働者の世界津々浦々に広がる、結びあった社会のネットワークなんです。(p.252)
浅尾はマルクスを引きながら、フェイスブックやツイッターなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)にたびたび言及し、SNSはマルクスが指導した国際労働者協会(第1インターナショナル)が目指した活動に似ていると言う。「マルクスが遺した膨大な手紙は『ジャスミン革命』『スペインM15』『OWS』『脱原発デモ』が生まれる過去ログとして読み直すことができる」(p.252)と書き、労働者の武器は「ネットワーク」だと指摘する。 労働者のたたかいはしだいに労働者の団結を広げ、労働者政党をつくって政権交代を目指すようになるのである(p.255-256)。 そして浅尾は書いている。 「いま公約違反や政党解体による政治不信が募ろうと、マルクスは『労働者の粘り強い共同の行動と討論は、必ず真の政権交代を実現させる』と言うだろう(エンゲルス「『共産党宣言』1888年版の序文」)。 そう、未だ階級闘争は継続中なのだ」
◆階級と階級対立の上に立つ旧ブルジョワ社会に変わって、各人の自由な発展が万人の自由な発展の条件であるような一つの共同社会が現れる。(p.259)
本項の後ろにもまだ21項目あるが、私はこの項目に本書の結論があると思う。浅尾も「この言葉が、若きマルクスの結論だ」と書いている。これはマルクスが展望した共産主義社会の姿である。それはどんな社会なのか。簡潔にその意味を論じた浅尾の言葉に耳を傾けよう。 「資本家の私的所有が廃止された社会。搾取のない社会。ピンハネ分が賃金に加算される社会。会社の財産が、労働者の共同所有となり、過労死や職場うつ病が減る社会。パワハラ社長は追い出され、搾取されていた労働日が休日としてよみがえる社会。自由時間と大幅な賃上げこそ『共同社会』の保障なのだ。この豊かさが、世界の貧困や自然破壊、戦争をなくすだろう。
夢物語かもしれない。しかしマルクスの構想は現実の上に立っている。資本主義では克服できない現実を見つめている」
おわりに
少し長くなったが、これでも『新解 マルクスの言葉』のごく一部に過ぎない。ほかにも「マルクスはこんなことも言っていたの!?」という言葉がたくさん掘り起こされ、現代の角度から読み直されている。例証や参考例にも内外の現実と言説から豊かな材料が集められている。ぜひ自分の目で確かめてみてほしい。
